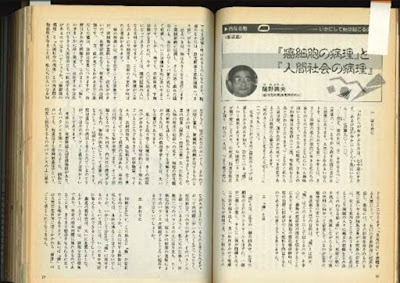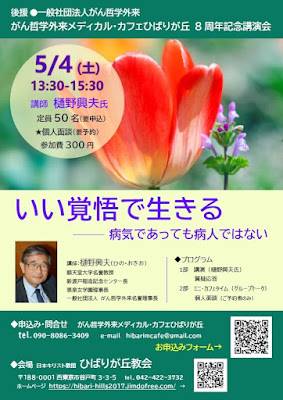第406回 相並んで、人間を組み立てる 〜 縦糸 と 横糸 〜

2024年5月27日、恵泉女学園の理事会、評議委員会に出席した。 5月28日は、新渡戸稲造記念センターから、順天堂大学保健医療学部 理学療法学科での講義『病理学概論』に赴いた。 授業では、教科書『カラーで学べる病理学』を使用して、今回は、『炎症』&『免疫のアレルギー』の箇所を音読をしながら進めた。 約120名の受講者で、真摯な姿勢で音読する生徒には、大いに感動した。 筆者は、『病理学』とは、『丁寧な観察力の修練』であると何時も述べる。 新渡戸稲造(1862-1933)が愛読したカーライル(Thomas Carlyle 1795-1881)の『汝の義務を尽くせ。汝の最も近くにある義務を尽くせ、汝が義務と知られるものを尽くせ』が、まさに、教育者の原点であろう! 生徒にとって【教育とは、すべてのものを忘れた後に残るものをいう(南原繁;1889-1974)】は、『人生の邂逅の非連続性の連続性』である。 矢内原忠雄(1893-1961)は、医者の子として四国の農村、現在の今治市に生まれ、神戸中学校から第一高等学校(東京)の法科に進学した。『一高の校長 新渡戸稲造先生との出会いは、自由の精神と人格の尊厳を植え付けました。 新渡戸稲造先生と内村鑑三(1862-1930)先生は、相並んで、私という人間を組み立てた、たて糸、よこ糸となっていると言っていいと思うんです。』と矢内原忠雄は語っている。 『がん教育は予防知識より心構えが大事』の取材記事が鮮明に思い出された。 【講義は『個性と多様性』&『賢明な配慮』の習得の場】であろう。 5月29日は、順天堂大学保健医療学部 診療放射線学科での講義『病理学概論』&『がん医療科学』である。『病理学概論』では、同じ教科書『カラーで学べる病理学』を用い、『がん医療科学』では【『がん細胞から学んだ生き方「ほっとけ 気にするな」のがん哲学』(へるす出版)】を用いて音読しながら進める。